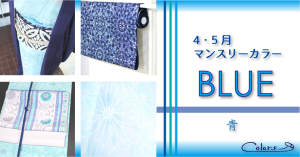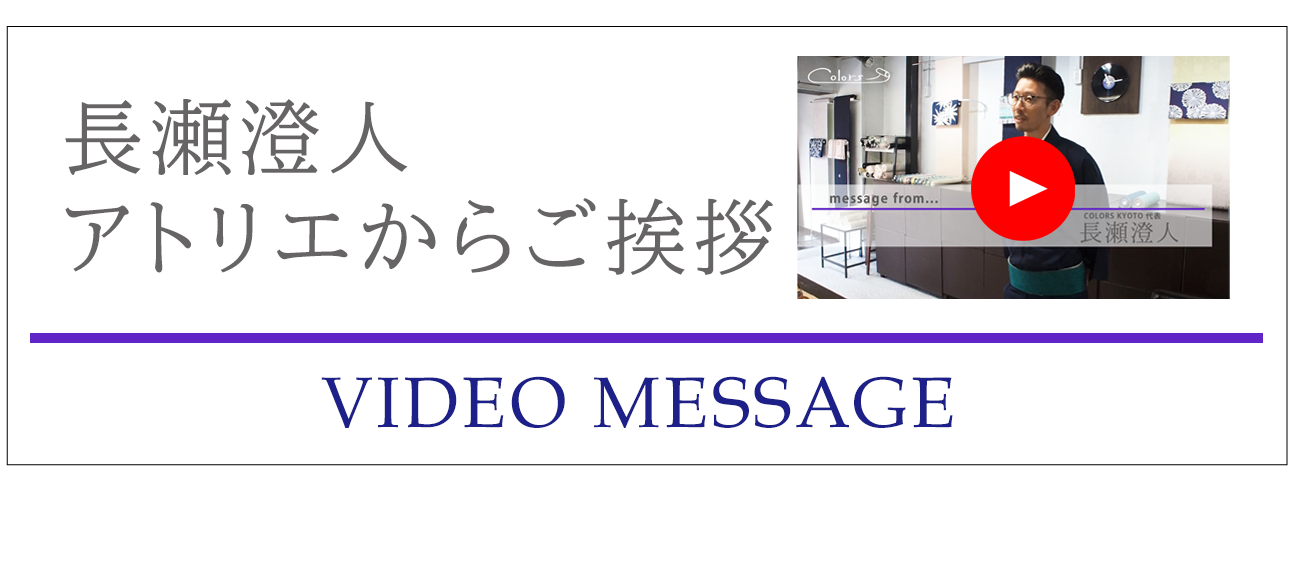染めの仕事

心地良い気候の時こそ、気を引き締めて染めることを忘れない、カラーズ京都の長瀬澄人です。
清々しい天候が続きますね。
着物を着るには絶好の環境ですが、同時に染めの作業にも絶好です。
気温から湿度から、少し収まった花粉から、何から何まで気持ち良く仕事ができる時期です。
梅雨が来るまでの短い期間ですが、しっかり働き、また着物も楽しみたいものです。
さて、その染めの仕事について。
多くの方が着物の染めの仕事というイメージとして、
「素敵な仕事だけど、大変そう。難しそう。」
と思っていただいているようです。
正にその通りです。
普段皆さんが目にする完成品の着物は、染物も織物もどれも魅力的で、その裏側という部分にはなかなか気が回らないし、もし興味があるとしても、それを知る術もあまりないものだと思いますので、興味本位で読んでいただければ幸いです。
型染工房の仕事内容は大きく分けて、
・絵の具場色合わせ
・板場柄付け着色
・依頼主や外注先との各種打ち合わせ
・デザインを起こす工房であれば図案作成や型紙の作成
などとなります。
他にも白生地、完成後の反物の検品管理業務や、型紙の管理、事務なども含めると、他にも雑務はたくさんあります。
カラーズ京都では、これらに加えて、ショップ業務も行っています。
通常、板場の人員(職人)、色合わせの人員(職人)、その他をまとめて行う人員(非職人、多くは親方や番頭、また親方の配偶者やパートタイマーなど)
という具合に、役割を分担して行う形です。
職人として一定の修行期間が必要となるのは、色合わせと柄付け着色ですね。
そして、実はこのどちらもできる職人は意外と少なくて、板場はできるけど色合わせはできない職人さん、または色合わせはできるけど板場はできない職人さん、というのがほとんどです。
さらに、板場と一言で言っても、使う材料や技法の違いが多岐にわたるので、刷毛で摺るのはできるけどヘラで糊を刷るのは苦手な職人さんや、その逆など、実に細分化していると言えます。
どれもマニュアルで伝えることができない特殊技能ばかりなので、とにかく経験を積んで身体に叩き込むしかありません。
また、各役割との連携というチームワークが、完成品のクオリティに大きく影響するため、相互に理解し合うことも非常に重要です。
このような体制は約40年前の、着物生産最盛期に確立したもので、決して今現在の減少した生産量ではバランスが取れないのが現実です。
今後は如何に少ない生産量でも継続していける形を作るか、それが至上命題だと言えます。
完成品は確かに美しいのが着物であり、それを作ることはとても素晴らしい仕事である反面、長年にわたる経験を積むことに堪えるだけの忍耐、さらには今後継続してゆくための創意工夫、そして何より着物が好きであるかどうか。
色々なことが要求される仕事ですから、簡単ではないですね。
気がつけば長文になりましたが、まだまだ書き足りないので、また続きは改めて。
カラーキャンペーン「ブルー」は、残すところ二週間を切りました。
ご検討中のお客様は、今月中にひとまずご相談ください。